
21トリソミー(ダウン症候群)とは?発生する確率・特徴・原因を解説
出生新生児の染色体異常症では最も有名なダウン症候群。21トリソミーと呼ばれるダウン症候群ですが、どんな病気か気になっている方も多いかと思います。本記事では、ダウン症候群の発生確率や原因などを解説してまいります。身体的特徴や疾患との向き合い方、公的な支援についてもまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の内容
21トリソミー(ダウン症候群)とは
21トリソミーについて概要や種類を簡単に説明いたします。
600人~800人に1人の確率で発生する性染色体異常
21トリソミー(ダウン症候群)は、出生時の600〜800人に1人の割合で発生すると言われている先天性の染色体異常症です。日本国内の患者数はおよそ80,000人いると言われており、染色体異常症の中で最も発生率の高い疾患です。
主な症状や特徴として、身体の発達の遅れや知的障害があげられます。
また、多くの患者に特徴的な顔つきや低身長、指関節の変形などがみられます。
寿命にかかわる合併症に注意が必要
この疾患の患者はさまざまな合併症が生じる可能性があります。
なかでも心室中隔欠損や動脈管開存などの心疾患は注意すべき合併症であり、これらが確認できた場合は手術療法や適切な処置が必要となります。
このほかにも食道閉鎖や十二指腸閉鎖など、消化管の合併症をきたす場合もあり、発覚した症状に対し適切な処置が必要となります。
これらのことから、21トリソミー(ダウン症候群)の健康維持には合併症の早期発見と、早期治療が重要と言えるでしょう。
標準型・転座型・モザイク型の3種類に分けられる
21トリソミー(ダウン症候群)の患者の染色体は、3つの型に分けられます。
それぞれの型の説明と症状に見られる特徴を解説していきます。
h4:標準型
標準型である21トリソミー(ダウン症候群)は、全体の約95%を占めています。22番ある常染色体のうち、21番目の染色体が上手く分離できず本数が増えてしまうことで生じます。
h4:転座型
転座型は全体の約3%に生じる型で、21番目の染色体が他の染色体に付着することで生じます。この型になるケースの半分は、両親のどちらかが均衡型転座(位置は違うものの健常な染色体数であること)を持っていることで起こると考えられています。
h4:モザイク型
モザイク型は正常な細胞核と21トリソミー型の細胞核が混在している型であり、全体の約2%にみられます。受精卵の段階で染色体の分離がうまくいかないことが原因です。
モザイク型の症例では、標準型よりも症状や特徴、合併症が軽くなる傾向があります。
21トリソミー(ダウン症候群)の特徴
顔貌や骨格など外見に特徴がみられる
21トリソミー(ダウン症候群)の患者には、外見に以下のような特徴がみられます。
- 鼻の位置が低い
- 耳の位置が小さく形が丸い
- つりあがった目
- 長い舌
- 後頸部の皮膚の余り
- 平坦な顔つき
- 舌と唇が厚い
- 顎が小さい
- 頬が丸い
筋力や身長に特徴がみられる
21トリソミー(ダウン症候群)の患者は低緊張になりやすく、全身的に筋肉量が低下する傾向にあります。
このため全身的に丸みを帯びた体型となりやすいです。
筋肉の発達が遅いため、立ち上がりや歩行などの運動発達が遅れる症例も多くみられます。
また、顎の緊張も低下することから口を開いた表情になりやすい特徴があります。
また、他の染色体異常症にもしばしばみられるように、21トリソミー(ダウン症候群)の患者は低身長になりやすい傾向があります。
発達障害や知的能力障害がみられる
患者は知能発達に影響がみられ、通常の小児のIQが平均値の100程度に比べて21トリソミー(ダウン症候群)の小児のIQの平均値は50程度と考えられています。モザイク型の患者の場合は、脳細胞中の正常細胞の数に比例して知能指数が高くなると言われています。
また、注意障害や多動症、自閉症などの気質がみられやすいことも特徴です。
急激退行症などによるコミュニケーション障害
青年期になると、「急激退行症」や「退行様症状」と呼ばれる状態に陥る方もおり、うつ病や引き籠りなどを起こす場合があります。
これらは健常人よりも脳内のアミロイドタンパクという物質が増加しやすく、若年のうちにアルツハイマー型認知症のような変化が生じることで引き起こされると考えられています。
合併症の発症リスクがある
染色体に起因する疾患は合併症を伴うことが多く、21トリソミー(ダウン症候群)も例外ではありません。
主な合併症としては以下の通りです。
- 心疾患(動脈管開存症・房室中隔欠損・心室中隔欠損・心房中隔欠損)
- 消化器疾患(十二指腸閉鎖・食道閉鎖・鎖肛鎖肛)
- 眼科疾患(白内障・斜視・乱視・近視・遠視・眼振)
- 耳鼻科疾患(中耳炎・難聴・閉塞性無呼吸)
- 糖尿病
- 白血病
- 排尿機能障害
- 甲状腺疾患
- 脱臼
- 偏平足
- 漏斗協
- てんかん・けいれん発作
心疾患や消化器疾患では、手術療法が必要となることも少なくありません。
白血病やてんかんなど、場合によっては長期の入院が必要となる合併症もあります。
体調の変化に注意したり、定期的な検診を受けたりし、予防や早期発見に努めるとよいでしょう。
他の染色体異常と比較して予後は良好
ターナー症候群やエドワーズ症候群のように、染色体異常症は短命となるケースが多くみられます。
21トリソミー(ダウン症候群)の患者も以前は短命でしたが、医療技術の発展により、平均寿命は60歳前後まで延びています。
21トリソミー(ダウン症候群)の発生原因
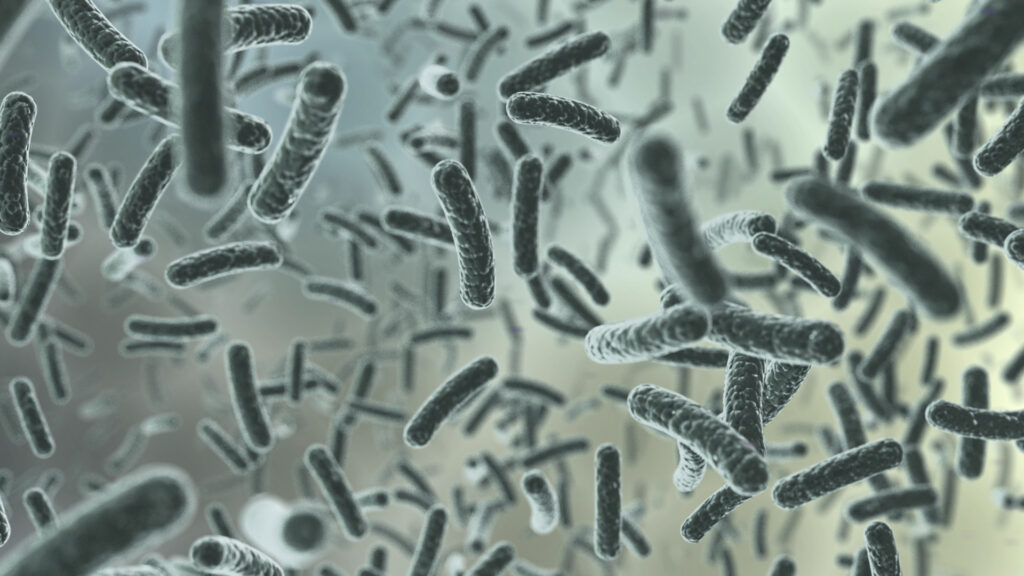
21番目の染色体数の異常により生じる
21トリソミー(ダウン症候群)は、疾患名にある通り、21番目の染色体の数が多いことで生じる疾患です。
21番目の染色体は通常2本のところ、患者には3本存在していることで症状や特徴が現れます。
染色体異常症は基本的に親から遺伝することはなく、患者の子供に引き継がれる割合も健常人と変わりありません。
転座型ダウン症の場合は遺伝の可能性もある
21トリソミーの3つの型のうち、転座型の場合のみ親から遺伝する可能性があります。
均衡型転座という、染色体の配置される位置が異なっている型があり、両親のどちらかがこの型である場合に遺伝することがあります。
高齢出産とダウン症の関係性
21トリソミー(ダウン症候群)の出生頻度は、母親の出産年齢と関係があります。
以下に出産年齢と患者の生まれる頻度をまとめます。
| 女性の年齢 | 21トリソミーの子が生まれる頻度 |
| 20 | 1667人に1人 |
| 25 | 1250人に1人 |
| 30 | 952人に1人 |
| 31 | 909人に1人 |
| 32 | 769人に1人 |
| 33 | 625人に1人 |
| 34 | 500人に1人 |
| 35 | 385人に1人 |
| 36 | 294人に1人 |
| 37 | 227人に1人 |
| 38 | 175人に1人 |
| 39 | 137人に1人 |
| 40 | 106人に1人 |
| 41 | 82人に1人 |
| 42 | 64人に1人 |
| 43 | 50人に1人 |
| 44 | 38人に1人 |
| 45 | 30人に1人 |
| 46 | 23人に1人 |
| 47 | 18人に1人 |
| 48 | 14人に1人 |
| 49 | 11人に1人 |
引用:厚生労働省 「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」報告書
21トリソミー(ダウン症候群)の治療
認知能力の改善が期待される治療について研究されている
21トリソミー(ダウン症候群)は先天性の染色体異常症であり、根本的な治療法は確立されていません。
しかし、フランスとスイスの研究所により、21トリソミー(ダウン症候群)患者に生じる症状を改善する治療が研究されています。
この研究によって、将来的に患者の認知症や嗅覚低下を改善する可能性があると期待されています。
21トリソミー(ダウン症候群)の検査方法
出生児が21トリソミー(ダウン症候群)かどうかを調べる検査方法について解説します。
エコー検査
エコー検査は腹部へ超音波を当て、妊娠中の胎児の様子を確認するための検査です。
21トリソミー(ダウン症候群)患者にみられる特徴として、胎児項部浮腫(NT)があります。
NTとは、胎児の後頸部にリンパ液が溜まった状態であり、NTが厚く見えるほど21トリソミー(ダウン症候群)を生じる確立は高くなります。
このほかにも、鼻の骨の有無や手足の長さからも疾患の可能性を検査することができます。
血液検査
精度はそれほど高くありませんが、血液検査からDNAを鑑定し、21トリソミー(ダウン症候群)の可能性を検査することができます。
羊水検査
エコー検査や血液検査で21トリソミー(ダウン症候群)の可能性が疑われた場合、より正確な診断結果を出すために羊水検査を行います。
検査は母体の腹部へ針を刺し羊水を採取する羊水穿刺を行います。
穿刺を行う際はエコー検査にて腹部を確認しながらの検査となります。ただし、母子への負担が少なからずあるとされており、医師の説明をよく聞いて実施することが重要です。
NIPT(新型出生前検査)による高精度な検査
NIPT(新型出生前検査)では、出生前に21トリソミー(ダウン症候群)の有無を高精度かつ安全に検査することができます。
母体の血液でのみ検査されるため、胎児への侵襲や負担はほとんどないとされています。
また、染色体異常症の中でも21トリソミー(ダウン症候群)の検査感度は非常に高いことが特徴です。
21トリソミー(ダウン症候群)の支援制度
21トリソミー(ダウン症候群)の患者の生活を支援する制度について解説します。
療育手帳・身体障害者手帳
療育手帳は知的障害のある方向けにつくられた手帳であり、障害福祉サービスや自治体・民間事業者のサービスを受けることができます。
身体障害者手帳は身体的な疾患や障害のある方へ交付されており、所持していることで公的なサービスなどを受けることができるものです。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当
特別児童扶養手当は知的・身体的に障害を持つ20歳未満の児童の保護者に支給されます。
支給される金額は、障害の重症度と保護者の所得により変わります。
障害児福祉手当は精神的・身体的に障害を持つ児童に支給される手当です。
受給には身体障害者手帳・療育手帳を所持していることや、障害の重症度も判断材料とされます。
小児慢性特定疾病医療費助成制度
染色体異常症のような小児疾患では、高額となる医療費負担を軽減するために支援制度が設けられています。
これは助成される基準を満たしている場合、保護者の所得に応じて自己負担額が軽減される制度です。
申請には医師の意見書が必要となるため、診断がついた段階で担当医師に相談することをおすすめします。
まとめ
本記事では、21トリソミー(ダウン症候群)の特徴や原因、検査方法について解説しました。国内の染色体異常症としては最も発生数が多いダウン症ですが、合併症に注意すれば予後は良好であり、健常人と変わらない社会進出を果たしている人もいます。検査の受検や正しい知識を身につけておき、子供が幸せに生活するサポートをしていきましょう。
参考文献
・厚生労働省 – 21トリソミーのある方のくらし
・MSDマニュアル – ダウン症候群(21トリソミー)
 03-6824-6527
03-6824-6527